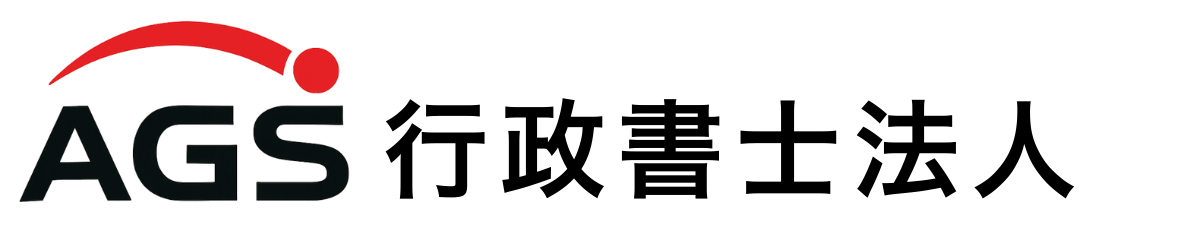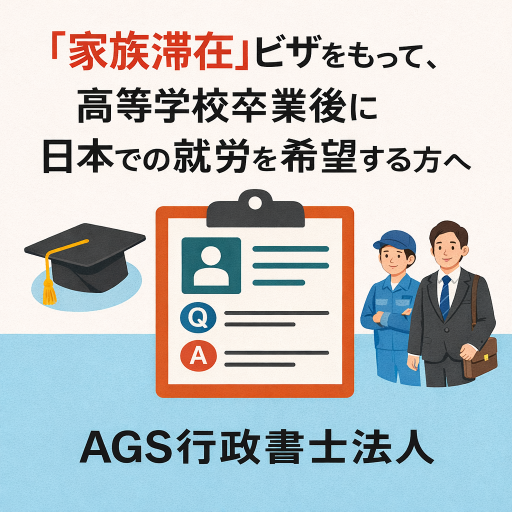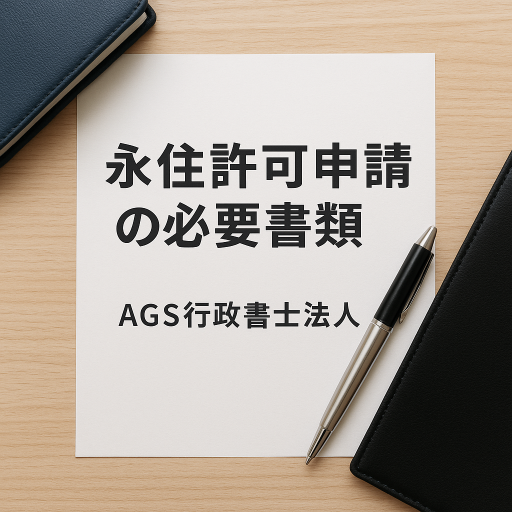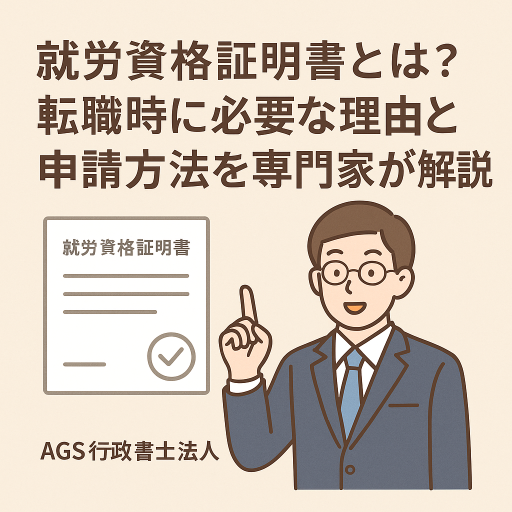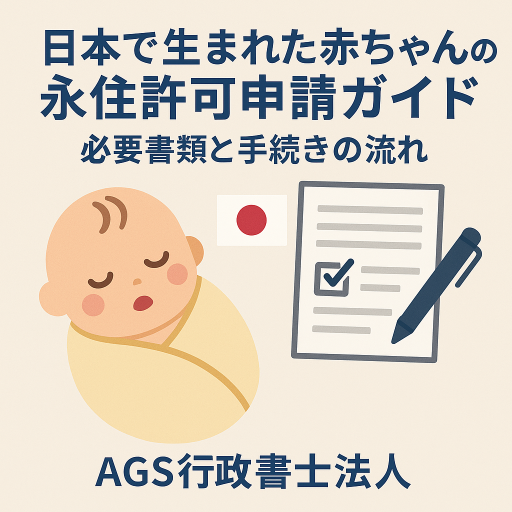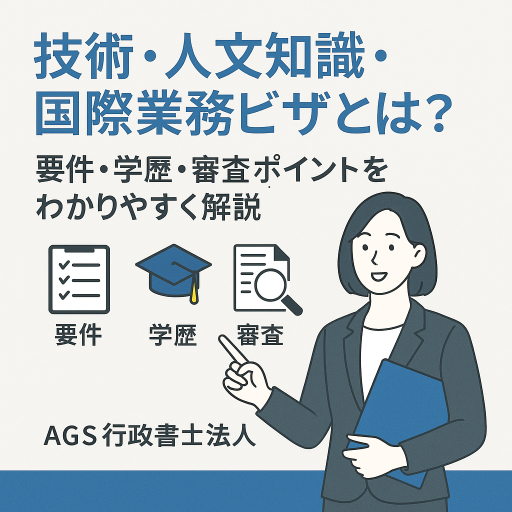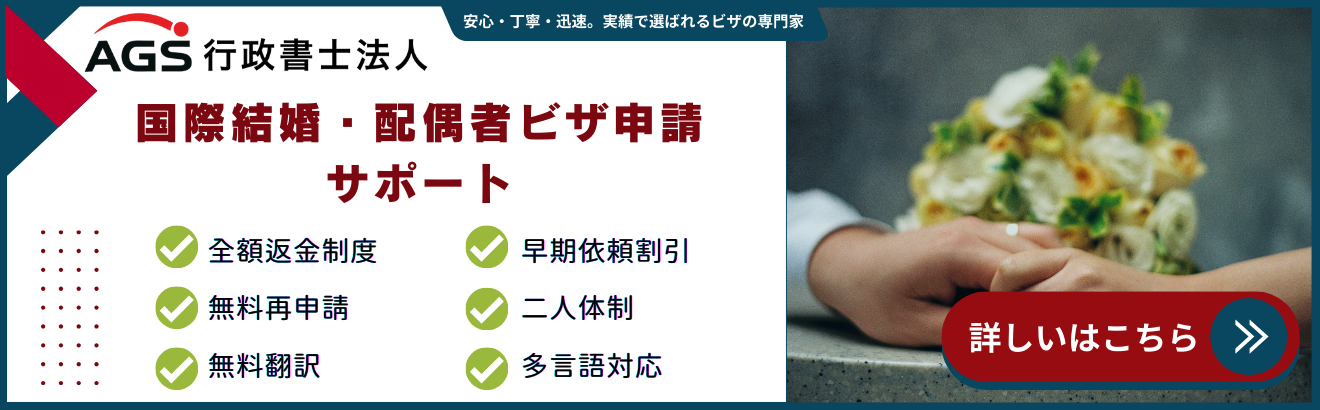【保存版】日本人の配偶者ビザとは?取得条件・必要書類・審査のポイントを専門家が解説

はじめに
日本でご家族と一緒に暮らすためには、「配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)」の取得が必要です。しかし、申請書類の準備や審査のポイントは思っている以上に複雑で、初めての方にとっては不安も多い手続きです。
このページでは、配偶者ビザの基本的な申請条件、必要書類、申請の流れや審査で重視されるポイントを、専門的な内容もできるだけわかりやすく解説します。これから申請をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
配偶者ビザとは
一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれている在留資格は、正式には「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」に区分されます。
この在留資格は、現に婚姻関係中の者が対象です。配偶者が死亡した場合や離婚した場合は含まれません。また、事実婚(内縁関係)の方は、この在留資格の対象にはなりません。
また、日本人または永住者の配偶者だけでなく、その子どもも条件を満たせば「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」として在留資格を申請することが可能です。
長く安定的に日本で暮らしていくために、国際結婚後の配偶者ビザの取得や更新、適切な申請準備が重要になります。
日本人配偶者ビザの特徴
在留活動は無制限
職種・業種を問わず、職業を自由に選択することができます。通学や、アルバイトを制限なく自由にできるし、会社経営についても日本人と同様に1人でも、資本金が少額も、事務所の制限なく自由に会社を設立することができます。
永住許可申請の条件緩和
「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人配偶者は、一定の条件を満たすことで、通常より短い期間で永住許可を申請することが可能です。
具体的には、婚姻関係を継続し安定した生活基盤を有している場合には、最短3年で「日本人の配偶者等」から「永住者」への在留資格変更を認められる可能性があります。
扶養されていなくても申請できる
日本人の配偶者等ビザは、「家族滞在ビザ」と違い、日本人配偶者に扶養されていなければならないという条件はありません。
申請人自身が収入を得て生活している場合でも、夫婦としての実態が認められ、安定した生計が確保されていれば申請が可能です。
日本人配偶者ビザの申請要件
1.国際結婚の手続きを完了していること
申請前提として、日本および相手国双方において、法的に有効な婚姻が成立していることが必要です。
具体的な婚姻手続や必要な書類(婚姻要件具備証明書等)は国ごとに多種多様ですが、相手国での婚姻手続が済んでいない場合には、配偶者ビザの申請は受理されません。
2.法律上有効な婚姻関係があること
「日本人の配偶者等」の在留資格は、事実婚・内縁関係には適用されません。
戸籍謄本(全部事項証明書)、婚姻証明書等により、法的に有効な婚姻が成立していることを証明する必要があります。
3.夫婦としての実態があること
単なる形式的な婚姻では足りず、実質的に夫婦生活を営んでいることが要件となります。
入国管理局は、交際経緯・交際期間・同居の有無・婚礼の有無・写真・通信履歴等の資料を通じ、実態を厳格に審査します。特に、交際期間が短い場合や年齢差が大きい場合には、偽装結婚の可能性があるとして、より厳格な資料提出を求められることがあります。
4.安定した生活基盤があること
配偶者ビザの審査においては、夫婦として日本で安定的に生活を営むことが可能か否かが重視されます。
一般的には、日本人配偶者の収入(課税証明書・源泉徴収票等)により立証しますが、日本人配偶者に扶養能力がない場合であっても、申請人本人に安定した収入や資産があれば要件を満たすことが可能です。
日本人配偶者ビザの審査ポイント
夫婦としての実体があることを示す資料が必要です。
単なる法律上の婚姻関係では足りず、社会通念上の夫婦として実際に共同生活を営んでいる事実を立証することが必要とされています。その婚姻の信ぴょう性を証明するために、各種資料の提出が求められます。
夫婦として生活を営むための十分な経済力が必要です。
婚姻の安定性と継続性が重要な判断要素となります。経済的基盤を示すために、申請人または主たる生計維持者の職業や収入を証明する書類を提出する必要があります。また、扶養家族がいる場合には、その扶養能力も審査の対象となります。
交際の経緯を説明し、資料で立証する必要があります。
審査では、結婚に至る経緯の合理性・継続性が重視されます。交際開始の経緯、交際期間、意思疎通の方法、挙式の有無、双方の過去の婚姻歴等について、客観的資料により立証が求められます。
ビザ更新時にも、婚姻の実体と経済力が審査されます。
日本人配偶者等の在留資格は、在留期間が満了する前に更新申請が必要です。更新審査でも、同居の実態や収入状況が重要視され、これらに不備があると不許可となることもあります。
日本人配偶者ビザ申請の必要書類
在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料
-
- 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- その他:預貯金通帳の写し、雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 等
-
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料
-
- スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)
- その他:SNS記録、通話記録等
-
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)
上記は一例であり、ケースによっては不要な書類があったり、追加で書類が求められる場合もあります。
在留資格変更許可申請
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料
-
- 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- その他:預貯金通帳の写し、雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 等
-
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料
-
- スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)
- その他:SNS記録、通話記録等
-
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
上記は一例であり、ケースによっては不要な書類があったり、追加で書類が求められる場合もあります。
在留期間更新許可申請
- 在留期間更新許可申請書
- 写真
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 日本での滞在費用を証明する資料
-
- 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- その他:預貯金通帳の写し、雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 等
-
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
上記は一例であり、ケースによっては不要な書類があったり、追加で書類が求められる場合もあります。
日本人配偶者ビザ申請の流れ
- お問い合わせ:電話、メール、LINE、WeChatなどから、お気軽にお問い合わせください。(相談サービスについて)
- 当事務所での対面相談:お客様の状況をしっかり把握し、オンライン面談にも対応可能です。
- 御見積書のご交付:同じ依頼内容であれば、御見積書の交付の後、報酬額が増えることは一切ございません。(報酬額について)
- 委任契約書の締結、報酬の入金:契約書の締結と報酬・着手金のご入金を確認後、業務を開始します。
- 申請書類の収集、作成:必要書類の収集を迅速にご案内または代行し、申請理由書などの作成まで丁寧に対応します。
- 入国管理庁に申請代行:入管へのオンライン申請にも対応し、追加書類があれば、速やかにお客様へご案内します。
- 在留カード等の取得代行:申請結果は速やかにご通知し、許可の場合は在留カード等を代行取得します。
- 残金の精算・無料再申請:立替金や実費、成功報酬の場合は残金を精算します。不許可の際は無料で再申請します。
日本人配偶者ビザに関るQ&A
Q:配偶者ビザの在留期間はどれくらいですか?
A:配偶者等ビザの在留期間は、通常「5年・3年・1年・6か月」のいずれかです。初めての申請や婚姻期間が短い場合には1年や6か月が付与されることが多く、婚姻期間が長く安定している場合や生活状況に問題がない場合には、3年や5年といった長い期間が許可される傾向があります。
Q:離婚や死別した場合でも「日本人の配偶者等」在留資格を保持できますか?
A:日本人の配偶者ビザは「現在も日本人と結婚していること」が前提条件となっているため、離婚や死別で婚姻関係がなくなると、在留資格は原則として失効してしまいます。速やかに、他の在留資格への変更を検討すべきです。
1 離婚した場合
婚姻関係が終了した時点で「日本人の配偶者等」在留資格を保持することはできません。ただし、状況により「定住者」(離婚定住)や「就労ビザ」など、他の在留資格へ変更申請が認められる場合があります。
2 死別した場合
配偶者が死亡した時点で婚姻関係は終了となるため、「日本人の配偶者等」の在留資格は対象外となります。ただし、子の監護や生活状況などを考慮し、「定住者」への在留資格変更が認められることがあります。
Q:日本人配偶者の収入が少ない場合でも日本人の配偶者等ビザは認められますか?
A:日本人配偶者の収入が少ない場合であっても、必ず不許可になるわけではありません。
日本人配偶者の収入が一定水準に満たない場合であっても、申請人本人が就労により安定した収入を有する場合日本人の配偶者等ビザが許可される可能性は十分にあります。
ただし、日本人配偶者も申請人もともに無職である場合は、婚姻生活の安定性・継続性に影響する経済力に問題があるとして、許可の可能性が低くなります。
結論として、日本人配偶者単独の収入不足=不許可とは限らず、世帯全体での生活維持能力が総合的に判断されます。
Q:夫婦が別居している場合でも、日本人の配偶者等在留資格を取得することはできますか?
A:単に別居しているという原因のみをもって不許可とはしていません。現代社会に婚姻概念の多様化を理由に、週1日しか同居していない夫婦でも、「日本人の配偶者等」在留資格を取得することができます。
申請人が日本人配偶者と別居している場合には、別居経緯、別居期間、別居中の両者の関係、お互いのコミュニケーションの有無、生活費の支給等の協力、扶助の関係の有無等について審査され、合理性が認められる場合には許可する可能性が高いです。
Q:夫婦の年齢差が大きい場合や、マッチングアプリにより交際になる場合には、日本人の配偶者等在留資格を取得することはできますか?
A:夫婦の年齢差が大きい場合や、マッチングアプリにより交際になる場合は、入国管理局から婚姻の信ぴょう性を疑われ、婚姻の安定性・継続性を厳格に審査します。交際経緯、生活状況等を可能な限り詳細に説明することがポイントです。
知り合った経緯、交際することになったきっかけ、交際の様態、外国人申請人が日本に来た回数、外国人申請人の親族と会った事実、結婚式や披露宴を開催した事実、現在の生活状況、将来の家族計画等、かつ、それを裏付ける資料(写真、、SNS、メール、通話記録等)を多く提出することがポイントです。
Q:日本人の子として出生した者や特別養子の場合でも、配偶者ビザを申請できますか?
A:はい、できます。「日本人の配偶者等」在留資格は、配偶者だけでなく、日本人の子として出生した者や特別養子も対象に含まれています。
この場合は、日本人との親子関係を証明する出生届受理証明書、特別養子の場合は特別養子縁組受理証明書などの書類を提出して証明する必要があります。
1 日本人の子として出生した者
「子」には、嫡出子のほか、認知された非嫡出子が含まれますが、養子は含まれません。出生の時に父や母のいずれか一方が日本国籍を有している場合、また、本人が出生前に父が死亡し、かつ、死亡の時に日本国籍を有している場合が、「日本人の子として出生した」に当たります。出生地点は特に限定がありませんので、外国で出生した場合も含まれます。他方、子の出生後にその父や母が日本国籍を取得しても、「日本人の子として出生した者」になりません。
2 日本人の特別養子
普通養子は含まれません。原則として15歳未満でなければ特別養子になれません。
Q:住民票などの証明書類は、自分で準備しなければならないのか、それとも事務所で対応してもらえるのでしょうか?
A:住民票などの各種証明書については、原則としてお客様ご自身にてご用意いただきます。もしご都合がつかない場合は、当事務所での代行も可能です。お気軽にご相談ください。
Q:日本人の配偶者ビザ申請の際、申請者本人が入国管理局へ出向く必要はありますか?
A:入管にお客様ご自身で行っていただく必要はありません。当事務所には申請取次資格を持つ行政書士が在籍しておりますので、ご依頼いただければ、入管への申請も含めてすべて代行いたします。
Q:遠方に居住している場合でも、日本人の配偶者ビザの申請をサポートできますか?
A:はい、地方や遠方にお住まいの方でも問題ありません。オンライン面談や郵送を組み合わせることで、来所いただかなくても日本人の配偶者ビザの申請をしっかりサポートいたします。
まとめ
配偶者ビザの申請では、婚姻の実態や生活の安定性など、書類だけでは伝わりにくい部分も審査の対象となります。そのため、正確な書類の準備と、申請内容を裏付ける適切な説明がとても大切です。
AGS行政書士法人では、これまで多数の配偶者ビザ申請をサポートしており、お一人おひとりの状況に合わせた書類作成や理由書の作成もお手伝いしています。不安な方や一度不許可になった方も、どうぞお気軽にご相談ください。

下記のボタンよりお気軽にお問合せください。
中国語対応可能・24時間受付中