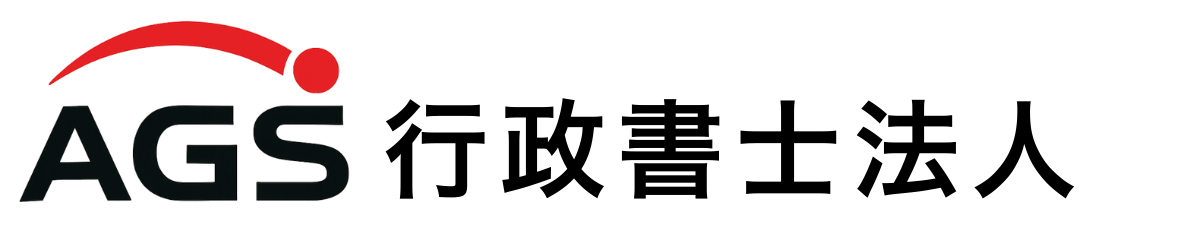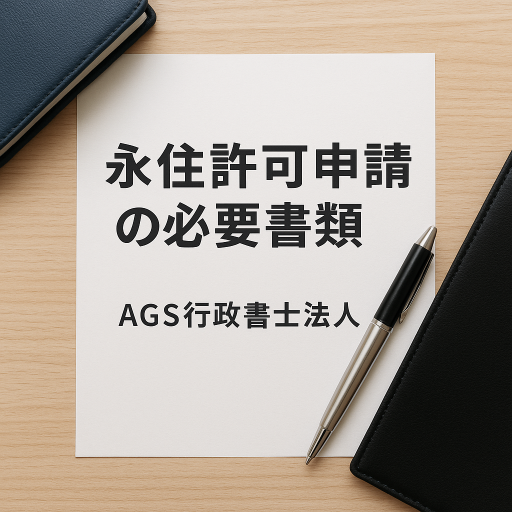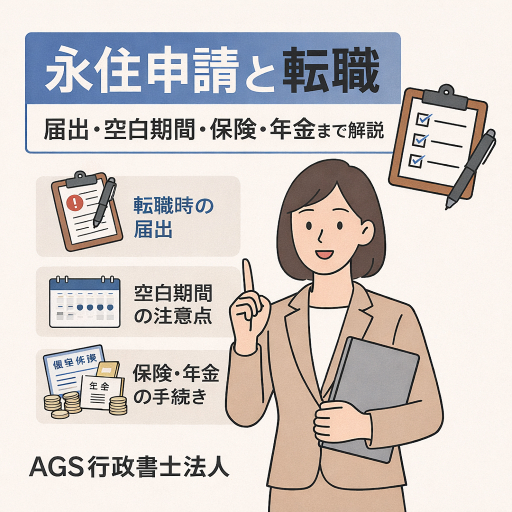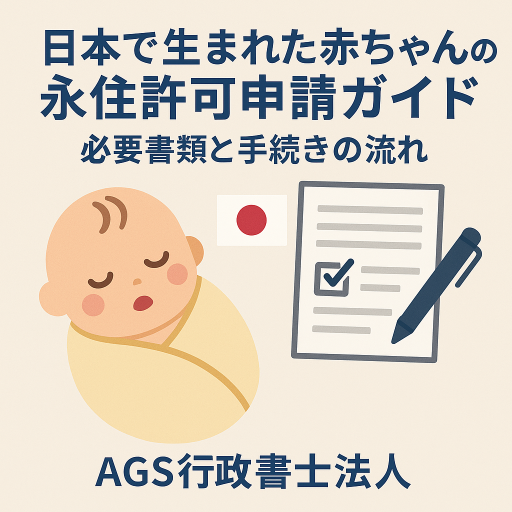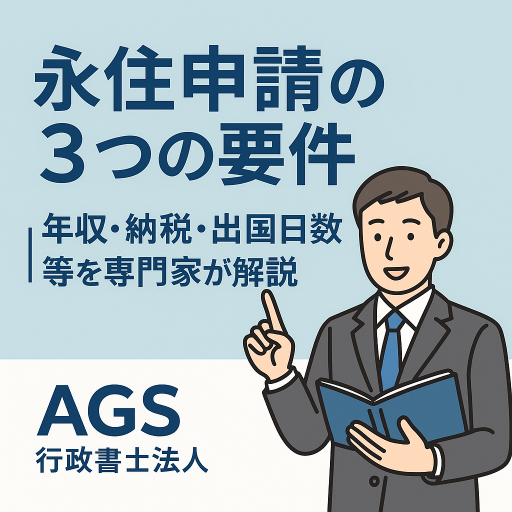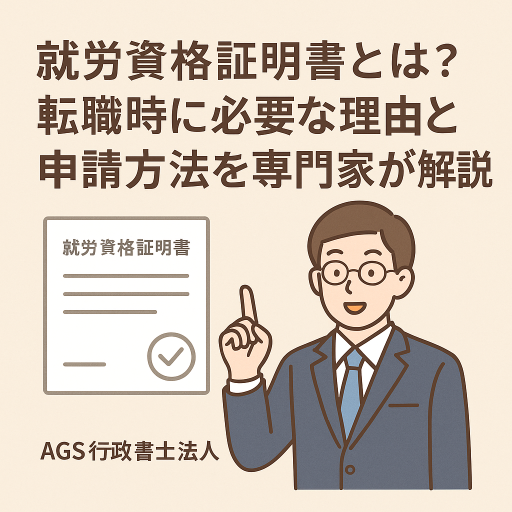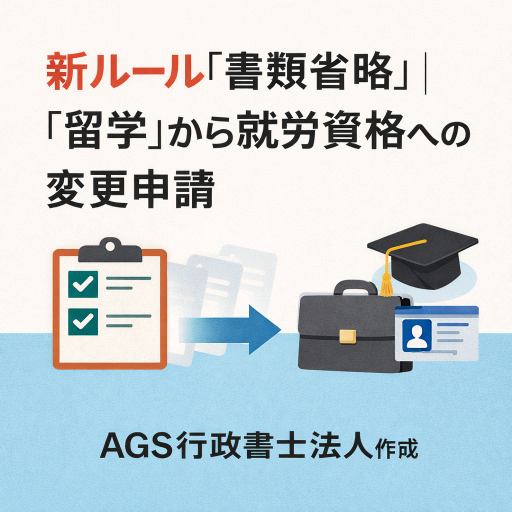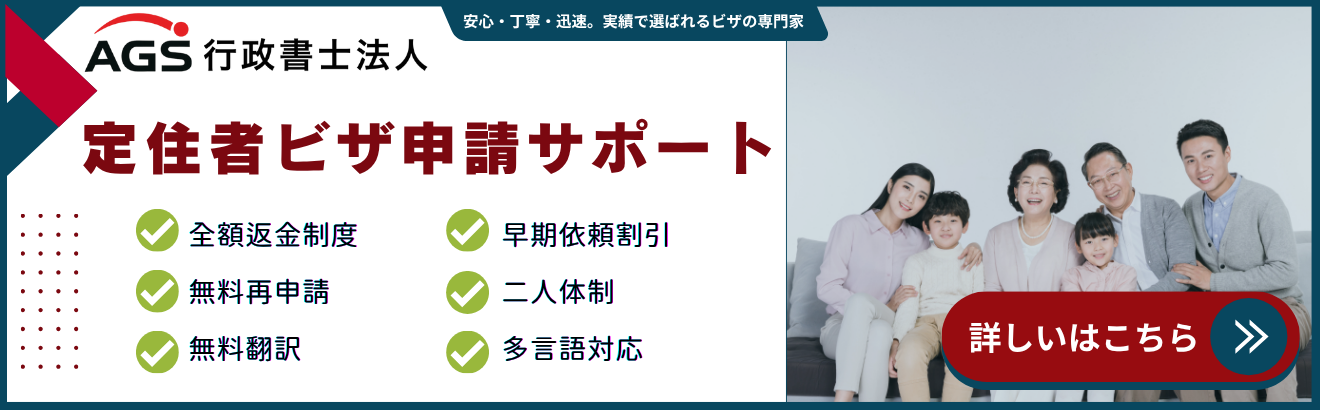【保存版】定住者ビザとは?取得条件・申請方法・審査ポイントをわかりやすく解説
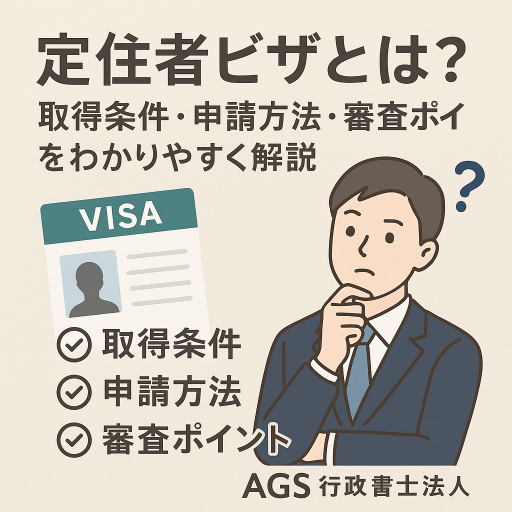
はじめに
「定住者ビザ(在留資格:定住者)」は、日本での生活を特別な理由により認められた外国人に与えられる在留資格です。
永住者と同じく就労の制限がなく、幅広い職種で働くことができますが、永住者と異なり「在留期間の更新」が必要です。
たとえば、「日本人の配偶者と離婚・死別した方」「日本人の実子を扶養する方」「日系人(二世・三世)」「日本人配偶者の連れ子」など、さまざまなケースがあります。
ここでは、定住者ビザの概要や種類から代表的な事例、申請に必要な書類、審査期間の目安などを詳しくご説明します。
定住者と永住者の違い
| 定住者ビザ | 永住者 | |
| 在留期間 | 1年・3年・5年 | 無期限 |
| 更新手続き | 必要 | 不要(在留カードの更新のみ) |
| 活動範囲 | 自由 | 自由 |
| 安定性 | 更新や再入国の際に個別審査が行われる。 | 永続的に居住できる地位。
再入国許可を取得すれば長期間の出国も可能。 |
| 主な対象者 | 日系人・離婚定住・死別定住等 | 長期滞在者からの昇格者 |
定住者ビザから永住権を目指すことも可能
定住者ビザは、永住者への「ステップ」として位置づけられることもあります。定住者として安定した生活を送り、税金や社会保険の納付・素行善良などの条件を満たせば、将来的に永住許可申請を目指すことが可能です。永住権を取得すれば、更新の手間がなくなり、転職や事業活動なども自由に行えるため、将来の生活基盤をより安定させることができます。
定住者ビザの種類
「定住者」は、次の2つのタイプに分類されます。
① 告示定住
法務大臣が定めた「定住者告示」に該当する場合です。たとえば、日系二世・三世、日本人の実子など、告示に明示された立場の方が対象です。
この場合、在留資格認定証明書の交付を受けて日本へ入国できます。
② 告示外定住
告示に該当しない場合でも、個別の事情を考慮して定住が認められることがあります。たとえば、日本人配偶者との離婚後も日本で生活を続ける場合などです。
この場合は、「在留資格変更申請」により定住者へ変更する形になります。
代表的な定住者ビザの事例
- 離婚・死別による定住(離婚定住・死別定住)
- 日本人の実子を扶養する外国人(日本人実子扶養定住)
- 日本人配偶者の「連れ子」を呼び寄せる場合
- 日系人(二世・三世・四世など)
離婚・死別による定住(離婚定住・死別定住)
対象者
許可要件
次のすべてに該当することが必要です。
- おおむね3年以上、正常な婚姻関係・家庭生活を継続していたこと
- 生計を維持できる資産または技能があること
- 日常会話に困らない程度の日本語能力
- 納税や届出などの公的義務を果たしていること
審査ポイント
- 別居期間があっても、夫婦の交流・支援関係が続いていれば「正常な婚姻関係」と認められることがあります。
- 離婚理由がDVなど正当な事情による場合は、定住者ビザが許可される可能性が高くなります。
- 離婚後14日以内に「配偶者に関する届出」を提出する必要があります。
「定住者」や「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格者との離婚であっても、許可される可能性はありますが、要件のハードルは高くなります:
- 「定住者」と離婚する場合:概ね5年以上の正常な婚姻関係・家庭生活の継続が必要。
- 「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格者と離婚する場合:概ね10年以上の継続が必要。
申請書類
- 申請書
- 証明写真(4cm×3cm)
- パスポートの写し
- 申請人の配偶者(又は元配偶者)の戸籍謄本
- 離婚届出受理証明書(離婚定住のみ)
- 身元保証書
- 世帯全員の記載のある住民票
- 理由書
- 雇用予定証明書又は採用内定通知書
- 在職証明書(自営業の場合は、確定申告書(控え)の写し及び営業許可書の写し(ある場合))
- 住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの。納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、これに加えて課税(非課税)証明書)。
- 預金通帳の写し又は預貯金残高証明書等
上記は一例であり、ケースによっては不要な書類があったり、追加で書類が求められる場合もあります。
日本人の実子を扶養する外国人(日本人実子扶養定住)
許可要件
次のすべてに該当すること。
- 生計を維持するに足りる資産または技能を有していること。
- 日本人との間に出生した子を監護・養育しており、次にいずれにも該当すること。
a. 日本人の子の親権者であること。
b. 現に相当期間、日本人の子を監護・養育していると認められること。
審査ポイント
- 婚姻期間が3年に満たない場合でも、定住者ビザへの変更が認められるケースは少なくありません。つまり、結婚生活の長さよりも「お子さんをしっかり育てているかどうか」「日本で安定した生活を送っているか」が重視されます。
- お子さんが日本国籍を持っていなくても、定住者ビザの対象になることがあります。その場合は、日本人の父親が認知していることが大切です。もし、認知が生まれてからしばらく経って行われた場合は、なぜ時間がかかったのか、これまでの親子の交流はどうであったかなどが、審査で確認されます。
- お子さんの日本での生活が続いていることも、非常に重要なポイントです。特に小学生や中学生などのお子さんの場合は、日本の学校に通っているか、または通う予定があるかが大切な判断材料となります。
- 経済的な安定も審査で重視されます。ただし、すぐに十分な収入がない場合でも、親族からの支援を受けながら働く予定や今後の生活計画がしっかりしていれば、許可される可能性はあります。
申請書類
- 申請書
- 証明写真(4cm×3cm)
- パスポートの写し
- 申請人が扶養する日本人実子の戸籍謄本
- 身元保証書
- 世帯全員の記載のある住民票
- 理由書
- 雇用予定証明書又は採用内定通知書
- 在職証明書(自営業の場合は、確定申告書(控え)の写し及び営業許可書の写し(ある場合))
- 住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの。納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、これに加えて課税(非課税)証明書)。
- 預金通帳の写し又は預貯金残高証明書等
上記は一例であり、ケースによっては不要な書類があったり、追加で書類が求められる場合もあります。
日本人配偶者の「連れ子」を呼び寄せる場合
対象者
審査ポイント
- ここでの「未成年」「未婚」「実子」という3要件はいずれも重要であり、特に年齢が高くなるほど上陸不許可となる傾向があります。
- 配偶者の入国後に、連れ子を日本に呼び寄せるような場合には、呼び寄せる側の経済状況(扶養するだけの十分の資力等があるか)が審査されるはもちろん、連れ子の実親によるそれまでの扶養実績も厳しく審査されます。
- 「未成年」とは日本法上18歳未満を意味しますが、本国法上すでに成年である場合には「扶養を受けている」とは認められない可能性があります。
- また、扶養者の経済力・扶養実績・連れ子の養育状況・将来の生活設計などが重視されます。
- 両親の婚姻の真実性、住民票上の居住地の一致なども審査の対象です。
- 申請理由書には、これまでの養育経緯や教育方針、生活設計などを具体的に記載することが重要です。
申請書類
- 申請書
- 証明写真(4cm×3cm)
- パスポートの写し
- 身元保証書
- 世帯全員の記載のある住民票
- 理由書
- 連れ子の出生証明書
- 親権証明する文書
- 雇用予定証明書又は採用内定通知書
- 在職証明書(自営業の場合は、確定申告書(控え)の写し及び営業許可書の写し(ある場合))
- 住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの。納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、これに加えて課税(非課税)証明書)。
- 預金通帳の写し又は預貯金残高証明書等
- 日本語能力を証明する文書(在留期間「5年」を希望する場合)
上記は一例であり、ケースによっては不要な書類があったり、追加で書類が求められる場合もあります。
日系人(二世・三世・四世など)
対象者
- 日本人の孫(二世・三世)
- 元日本人の実子、孫
- 日系三世の扶養を受ける日系四世(一定の条件下で)
審査ポイント
- 日系人に関する申請では、父母・祖父母などの身分関係の証明が重要です。戸籍・公文書・古い証明資料・写真など、関係を証明できる資料をできるだけ多く収集して確認することが必要です。
- 日系四世の場合、「定住者」または「特定活動」で認められるケースがあります。
申請書類(申請人の方が日系3世である場合)
- 申請書
- 祖父母(日本人)の戸籍謄本
- 婚姻届出受理証明書(祖父母及び両親)
- 死亡届出受理証明書(祖父母及び両親が死亡している場合)
- 申請人の出生届受理証明書
- 身元保証書
- 世帯全員の記載のある住民票
- 外国が発行した祖父母及び両親の婚姻証明書
- 外国が発行した両親及び申請人の出生証明書
- 祖父母及び両親が実在していたことを証明する公的資料
- 申請人が本人であることを証明する公的な資料
- 外国が発行した申請人の婚姻証明書(婚姻している場合のみ)
- 雇用予定証明書又は採用内定通知書
- 在職証明書(自営業の場合は、確定申告書(控え)の写し及び営業許可書の写し(ある場合))
- 住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの。納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、これに加えて課税(非課税)証明書)。
- 預金通帳の写し又は預貯金残高証明書等
- 日本語能力を証明する文書(在留期間「5年」を希望する場合)
上記は一例であり、ケースによっては不要な書類があったり、追加で書類が求められる場合もあります。
「日本人の子として出生した者」(親)が日本国籍を有していた(または有していたことがある)場合、
- 日本国籍を有している間に生まれた子は「日本人の配偶者等」として、
- 日本国籍を有しない間に生まれた子は「定住者告示3号」に該当する「定住者」として、それぞれ在留資格を取得することになります。
定住者ビザの審査期間の目安
申請内容や地域によって異なりますが、一般的には2か月〜6か月程度が目安です。書類の不備や審査内容が複雑な場合は、さらに時間がかかることがあります。
よくある質問(Q&A)
Q1. 定住者ビザと永住者ビザの違いは?
A. 永住者は在留期間の制限がなく、更新の必要がありません。
一方、定住者は1年・3年・5年など期間が決められており、定期的に更新手続が必要です。
Q2. 定住者ビザの更新は難しいですか?
A. 生計の安定、日本語能力、公的義務の履行などが維持されていれば、更新は比較的スムーズです。
Q3. 定住者ビザの申請は自分でできますか?
A. 可能ですが、申請理由書や証明書類の整理が複雑なため、行政書士など専門家に依頼するのがおすすめです。
Q4. 審査期間中に仕事を続けられますか?
A. 在留期限内であれば、これまでと同じ在留資格で活動を継続できます。
Q5. 離婚してすぐに定住者ビザを申請できますか?
A. はい。離婚届を提出後、速やかに「在留資格変更許可申請」を行うことができます。
定住者ビザ申請の流れ
- お問い合わせ:電話、メール、LINE、WeChatなどから、お気軽にお問い合わせください。(相談サービスについて)
- 当事務所での対面相談:お客様の状況をしっかり把握し、オンライン面談にも対応可能です。
- 御見積書のご交付:同じ依頼内容であれば、御見積書の交付の後、報酬額が増えることは一切ございません。(報酬額について)
- 委任契約書の締結、報酬の入金:契約書の締結と報酬・着手金のご入金を確認後、業務を開始します。
- 申請書類の収集、作成:必要書類の収集を迅速にご案内または代行し、申請理由書などの作成まで丁寧に対応します。
- 入国管理庁に申請代行:入管へのオンライン申請にも対応し、追加書類があれば、速やかにお客様へご案内します。
- 在留カード等の取得代行:申請結果は速やかにご通知し、許可の場合は在留カード等を代行取得します。
- 残金の精算・無料再申請:立替金や実費、成功報酬の場合は残金を精算します。不許可の際は無料で再申請します。
まとめ
定住者ビザは、日本に特別な事情をもって生活する外国人に対して与えられる柔軟な在留資格です。申請にあたっては、婚姻・家族・経済・日本語など複数の要素を総合的に判断されます。
ケースによって必要書類や審査期間も異なるため、正確な準備と説明が重要です。
当事務所では、離婚定住・日本人実子扶養・日系人・連れ子呼寄せなど、あらゆる定住者ビザのご相談・申請を丁寧にサポートしております。ご不明点がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

下記のボタンよりお気軽にお問合せください。
中国語対応可能・24時間受付中